
瀬降り物語 特集1

自然へのラヴコール ―中島貞夫は語る―
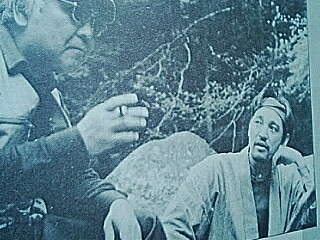
製作直前の中止
「瀬降り物語」は、「くノ一忍法」(64)で映画監督としてのスタートを切った中島貞夫の二十年にわたる思いの結晶である。四国山脈を大ロケーションしたほぼ一年間の撮影が昨年暮れに完了、二月にはベルリン国際映画祭に出品、そして今は五月公開を待つばかりとなった中島監督に「瀬降り物語」誕生までの紆余曲折を語ってもらった。一つの事を成し遂げた監督の姿はすがすがしく、そして晴れやかだ。「三十九年に僕は『くノ一忍法』でスタートしてるんですね。まあ、デビューするようなシャシンじゃないんですね、『くノ一』は。たまたま映画界がああいう状況で。今の(岡田茂)社長が、東京の所長から京都へ来ましてね、時代劇はダメだったでしょ、何か考えろって言うんでね、自分でやるなんて考えずに『くノ一』の企画を出したんですよ、半分いい加減な気持で。そしたら何となくやる気運になっちゃって、誰も撮るやついないからお前撮れということになっちゃった。で、しょうがなく倉本(聡)のところへ電話して助けてくれって言ってね、あいつ引きずり込んで、そして二本やったんです。これは興行的にもうまくいったんですが、あんまりノリノリでやったんじゃないということを(所長も)知ってて、何か好きなもの一本やってもいいということになってね、それでこの企画を出したんですよ」昭和三十年代末から四十年代はブルドーザーが日本列島をさかんに改造し始めていた時代だ。山野をさすらう〝山の民〟を描くというよりは、そうした自然破壊に対する反・テーゼがむしろ主眼だったと監督は言う。が、何故そのテーゼが山の民と結びついたのだろうか。「彼らに対する興味はなかったわけじゃないんですよ。田舎(千葉)にいた時ね、醸造関係だったから、家が。毎年、来てたことは来てました。箕直しにね、冬。九十九里であったかい地方だったから冬回ってくるという地域だったんでしょうね。蔵の前でね、毎年同じ人が来てやってたのを覚えてますね。三日ぐらい来るんですよね。全部直し終わると米持ってったり、味噌持ってったりしてね、またどこかへ行っちゃう。米を袋に入れてやったりしたのは覚えてますね」が、そうした光景は戦前までだったという。替わって、戦後すぐに読み始めた三角寛の小説が彼らへの興味を募らせることになる。中学生くらいで読むにはちょっと猟奇的で、なかなか面白かったそうだ。しかい、映画にする時は、猟奇的ではない線でできないものだろうかと考え、倉本聡と共同で脚本を練る。その脚本は映画化が中止になってからキネマ旬報にも掲載された。「岡田さんはOKだったんですよ。岡田さんにすれば少し変わったものをやってもいい頃だろうという気持もあったんじゃないですかね。OKが出て、キャスティングも全部やって、それこそ親分(ヤゾー)、西村晃とかね。それがね、なくなった大川(博)さんが、もうとんでもないもの持ってきたって。滅多に脚本なんか読まない方なんですがね、何の拍子か読まれちゃって―」映画は突如中止となる。その時は相模湖の上流をロケ地に決め、プレハブを建てるために整地作業も進められていた。クランク・イン寸前の中止命令。理由は、「わけのわからないシナリオ」ということだった。ショックは大きかった。「映画をやめようかなってところまでいっちゃって、落ち込んじゃって―。それで、二、三ヶ月ふて寝してたですがね。でも、ふて寝しててもしょうがない。二、三ヶ月ふて寝してるとやることなくなっちゃったから、神波(史男)ちゃんらと釜崎に泊り込んでシナリオ作ったりなんかして、二本ぐらいダメだったな。(岡田)所長が、じゃ読んでみい!と。読みますとね、おい、オレのとこ映研とちがうわいとかね。当時、社員ということもあって映画化されないとお金くれないわけですよね、給料もらってるから。そうすると他の人に頼めなくなっちゃってね。それでボチボチ京都市内で取材しながら書いたのが『893愚連隊』。あれも半分ヤケクソで―(笑)」
力強い主人公
山の民の企画が潰れたのが六十五年。ふて寝季節を経て。翌六十六年から中島監督の旺盛な映画作りが始まる。以後、今日まで七十五年を除いて毎年映画を作り続ける。この間、二回ほど復活への働きかけはしたものの、山の民の話は企画としては持ちあがってこなかったという。それが二年前から実現へと向かい始める。「どうにも身動きができなくなってくる時なんかに、こんなの(山の民の映画)できないかなって思いはありましたよね。あんまり抱えこむってのはいいことなのか、悪いことなのかわからないけど、まあ自分自身で自分をある程度規制するためにも―。五十までは何でもやるけど、五十になったらできなくなるなんてね、言ってる手前もあって、この辺でひとつ何かできないとシンドイなあという気はしてたんですけどね。気がついたら一番最後までヤクザ映画やってるし(笑)」「瀬降り物語」の準備が始まった頃、「序の舞」(84)の話が飛び込んでくる。最初はあまりノリ気ではなかったが、自分を試してみる意味でやってみようということになった。京都で女優との接触が多かったことも理由の一つだ。テレビの大奥ものを手がけていたという実績もある。飲むと途端に色っぽくなることを発見して、中井貴恵を「人生劇場」(83)で起用した中島監督である。「序の舞」では名取裕子のムンムンする女の体臭が画家の性を感じさせた。「瀬降り物語」でもドラマを担うのは女たちだ。村の若者(光石研)と結婚しようとして、山の民と村人が衝突する原因を作った娘ヒデ役の河野美地子に出会ったのは、一昨年、中島監督がミス映画村の審査委員長をしていた時だ、その母クニは二十年前のシナリオではもっと小さい役だったが、今回新たに書かれたものでは村の女(永島映子)と対立する山の民のいわば代表ともいうべき重要な役。今までこういう役をしていない女優をという観点から藤田弓子が選ばれる。そして連れあいの亀やん(殿山泰司)に先立たれたクニが激しくその体を求める親分(ヤゾー)に萩原健一が決まる。ドラマを女たちに任せ、自分は自然そのものと化して共同体を支えるという静かで力強い主人公だ。「僕はショーケンというのは、あんまりね、踊らん方が役者としていい線が出るんじゃないかと思っていたんです。で、それを(映画に)入る前にちょっと彼に話したの。男っていうのはヤクザ映画じゃないけど、うしろ姿がよかったら、もう全ていいからというみたいなことを言って。彼、踊る気配がありますんで、それなしでいっぺんやってみようと。まあ、おこがましいけど、彼の今までみんなの前に出してないものが出ればと思って」各親分(ヤゾー)の上に位置するクズシリの一人に扮した室田日出男は前からやりたいと言っていて、今回、噂を聞きつけるや駆けつけて来たそうだ。スタッフ・キャストが合宿したのは愛媛県北宇和郡松野町の国立公園滑床渓谷。二十年前に整地作業まで行なった相模湖周辺は現在ではすっかり様変わりして使えなかった。が、その時整地作業に加わっていた仲間の一人が今では四国で土建会社の専務になっていて、プレハブを建てたり河原の整地をするのに大いに協力してくれたという。もちろん、町役場も専門の係をつけてくれ、水道を谷川から引いてくれるなど、非常に好意的だったとのこと。国立公園内での映画撮影は現場を変えない限り、という条件で許可がおりる。プレハブを建てた所は、たまたま観光開発が予定されていた場所で、駐車場のための地ならしがされていたので好都合だった。営林署ともずい分接触したという。
挽歌の始まり


山の民を山から追い出していったのは昭和十一年の国家総動員法だ。映画の背景はその二年後である。山の民と村人の衝突、その上に立って人々を戦場へと駆り出していった国家の姿が映画の後半になるとくっきりと浮かびあがる。国家批判の映画に国の機関が協力するのは面白い。が、中島監督は「営林署は関係ないでしょ」と、当方の思い込みを笑いながら、しかし当時の国家が山の民を消滅へと導いていったことを描くためにあの昭和十三年代を背景にしたのだと語る。「僕もヤクザ映画やってまして、現代ヤクザだけじゃなく股旅でもそうなんですが、権力が一番嫌うってのはさすらいだということを知っている。自分たちの手の内に入ってないっていうことで。ですから、この素材を扱う時には必ずその問題が出てくると思ってました。現実に彼らが何故いなくなったのかという問題が出る時は、国家総動員法から徴兵制の強化から統制経済までが影響してますよね。それが一番鮮明に出る時代ということであの年代を選んだんですけど。そうなると徴兵制が絡んできますし、徴兵拒否までいかないと話が収まらなくなる。また、ああいう大自然の中で生きるということと、戦争に駆り出されるということは正反対のテーマでね。ドラマを作る時の根幹はそこにありましたね」この映画の終わりは、一種の挽歌の始まりだと監督は言う。自然と人間との関わりも、人間の方から失われていくのだ、と。が、だからといってこの映画を狭苦しい図式の中に封じ込めてしまっては、自然を、移り変わる四季とともに捉えた意味がなくなってしまうと心配する。撮影は「ふるさと」の南文憲だ。映画の前半は、ドラマも身を伏せて、山の民と自然の静かな営みが描かれる。だが、もっと自然の厳しさがあってもよかったのでは、という感想を寄せた人もあったという。「彼らの生活が、できるだけ危険を遠ざけて生きようとするものだから、それでもなおかつかかってくる程度のことじゃないとね。あんまり意識的に映画的におそろしげな自然を描いてもしょうがないという気があった。できるだけ自然に寄り添う、それがまあ自然の中に生きる人間の姿だろうということで、その辺のあざとさっていうのはできるだけ避けてみたんですけれどもね」映画の始まりは結婚の儀式からだ。人間にとっての儀式は節目であり、晴れの部分である。そこから入っていって、どんどん日常的なことを追っかけていくというやり方をしたのは、儀式が彼らの生きていく基盤や歴史まで描く一番いい方法だと考えたからだ。しかし、ドラマ部分を後半にぐっと寄せたのはどうしてだろう。「いろんなやり方があるだろうけれど、徹底的にいっぺん、キャメラがどのくらいつかまえられるか試してみようという気がありましてね。光線を徹底的に狙ってみよう、と。だから朝の追っかけ(萩原健一が山に入ってきた光石研の後をつける)のとこなんか、一日ワンカットずつですよ、朝のある時間帯だけ狙いますんで―。役者も時にはイライラするくらい今度は光線を狙いました。一つには映画をここまでやってきて、何もかもがドラマ主義になっちゃって、テーマがあって、ドラマがあって、表現手段としての映像が、少し軽視されてるんじゃないかという(気がした)。日本の映画の作り方の、今の状況の中で、時間に追われ、予算に追われてやると、どうしてもそこまで配慮しきれない。で、お話や役者の力で見せちゃう。そうじゃなしに、一つ一つ目の前にある画面そのものの力、ワン・ショット、ワン・ショットの持つ力というのが集積されてくる時に、表現手段としての映画ってのがあるんだって」それが劇場でかける映画の力だ。お金はしょうがないけれども時間だけは下さい。そう言ってこの映画に取りかかる。写し出された自然は美しくそして気品がある。「変な言い方すると、自然に対するラヴコールですよ。実際撮っていきますと、ますますそうなってくる。それにこちらの望む条件というのはなかなか出てこないわけですよ。思いが募るっていうのかな、振られれば振られるほどというのがあるでしょ、結局、あの感じですね」大水のシーンは特に大変だった。データを調べて、梅雨の後半が出水率が高いというのでその頃を狙って出かけたところ、一週間毎日ピーカン。皆もだんだんいらついてくる。なにしろ雨を待つ以外することはないのだ。そして、待ちに待った雨が降る。「じゃあ行こう!と。ところがメシ食ってるまに減水してるわけです(笑)。で、その日失敗する。翌日はこっちも多少過酷になんなきゃいかんわけですね。悪いけどみんな今日、メシ食わずに行ってくれって。光線狙ってますでしょ、とにかく二、三時間で、朝メシ食わずにやってもらう。そういうことしないと撮れないわけですよ」
自然と人間の関係
自然に惚れ込んだ監督は、まるで恋人のことを話すかのように目を輝かせて山や川、そして光と雨について語る。山野をさすらい、川のそばに瀬降りを構えた山の民は、自然との同殿共床をはたした人々であったのかもしれない。かつて、〝さすらいの山の民〟といったような呼ばれ方は一度としてされなかったであろう人々へ寄せる監督の思いは、自然への思いと同質であるような気がする。そこには憧れにも似たひたむきな愛が感じられるのだ。が、現実には異なった生活習慣を持つ人々へ抱く多数派社会の差別意識がかつて存在したし、今もその問題が解決しているわけではない。そこを避けてしまったら、この映画はひどく空々しいものになっていただろう。また山の民の側に立ったり、両方の側にほどよく立ったりしたらもっといやらしいものになったに違いない。しかし、この映画はどちらの誤謬もおかさず、すがすがしく自由である。対立はある。藤田弓子のクニが娘のヒデと村の男の結婚をその男の兄嫁に迫るところでは、兄嫁の永島暎子が「去ね、去ね!」と激怒し、村人をあおって自分たちの祭りを台無しにしたクニを襲わせる。が、一方で山の民は里に住む人間たちを大層軽蔑している。それは山に住む彼らが自然と一体化しているからではないだろうか。そして、ドラマ部分をやや押さえ気味にして、自然の姿をワンカット、ワンカット大事にしながら撮っていった中島監督は、そのことを固く信じているからこそ、何よりも自然を捉えようとしたのだろう。「今回のドラマをどう見るかというドラマツルギーの問題がある。頭から終わりまでを一つのドラマとして考えるかどうか。いや、むしろドラマは後半にあればいいと。ある意味で自然と人間というヤツをぐんぐんぐんぐん押していく中でひとりでにドラマが出てくるような作り方をしてみたいと。そういう意味で四季も狙いたいし―。要するに全体見終わった後で、人間のドラマということと、もう一つは自然と人間の関係というのが、理屈じゃなしに画面でね、何か頭の中にイメージとして定着してくれればいいなあ、と。今まで僕がやったドラマツルギーの中ではかなり特殊なやり方はしてみたんですけどね」ベルリンでの上映前には、内容的にどの程度理解してもらえるかということと、気候風土の違い、たとえば雪の中で登場人物がわりと軽装でいることなどがヨーロッパの人にわかってもらえるだろうかという二点が気がかりだったそうだ。が、記者会見で出てきたのは音楽の使い方。これは出品のために審査を受けた時にも出てきた問題だという。もっと日本的な音楽を彼らは要求する。日本に対する固定観念を感じたそうだ。内容への理解はかなりよかった。「序の舞」が昨年タシケント映画祭やアジア映画祭に出て賞を受けていたので、今回も多少の期待はあったと笑いながらベルリン映画祭を振りかえる。シドニーとインドから映画祭への招待があった。自国が抱えている問題とも関連があると、インドの委員は特に関心を示したそうだ。そういう意味でいろんな話が聞ける映画祭へはチャンスがあればどんどん出かけた方がよいという。そしてまた、東京国際映画祭を機会に、今の日本映画を見たがっている海外の映画人に日本映画を見せることもやっていくべきだと熱っぽく語る。宿題の一つを果たした誇りと満足感、そして公開を前にした期待と緊張がさわやかな印象を与える中島貞夫監督は今、世界を見つめている。
| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||
